症例
30代女性。数年前から腹痛と下痢が繰り返し出現。大腸内視鏡検査では器質的異常は認めず、採血や便培養も異常なし。仕事の繁忙期や人間関係でストレスが強い時期に症状が悪化する。内科で消化管機能調整薬を処方されるも効果は限定的で、不安感も強くなり受診を繰り返している。
→ 典型的な「過敏性腸症候群(IBS)」の一例です。
脳腸連環(brain–gut axis)の視点から
この患者さんの症状は「腸の異常」だけでは説明できません。
- ストレスによる自律神経の乱れが腸管の運動や知覚に影響
- 腸内細菌のバランスの変化が免疫応答や腸粘膜透過性に関与
- 腸から脳へのフィードバックで不安や痛みの感受性が増幅
このように**脳と腸が双方向に影響し合う「脳腸連環」**が、IBSの病態の背景にあると考えられています。
臨床での治療アプローチ
IBSの治療は「腸」と「脳」の両面からアプローチする必要があります。
- 腸へのアプローチ
- 食事療法(低FODMAP食は国際的にエビデンスあり)
- 薬物療法:便通異常のタイプに応じてリファキシミン、リナクロチド、ルビプロストンなどを選択
- 脳へのアプローチ
- 心理的介入(認知行動療法、腸催眠療法)は有効性が示されています
- 抗うつ薬(TCA, SSRI)は低用量で内臓知覚過敏の改善効果もあり、併存する不安・抑うつにも対応可能
最近の研究から
2025年の Nature 論文では、腸内細菌の影響を受けたT細胞が脳の特定部位(SFO)に移動し、食行動を制御することが報告されました。
「腸内細菌 → T細胞 → 脳 → 行動」という経路は、IBSの症状と強く関係している可能性があります。
まとめ
- IBSは器質的異常がないにもかかわらず強い症状を呈し、患者さんの生活に大きな影響を与えます。
- 脳腸連環(神経・免疫・腸内細菌)はその病態の鍵を握っています。
- 治療は食事・薬物・心理的アプローチを組み合わせた「多面的介入」が必要です。
- 最新研究により、今後は免疫を標的とした新しい治療法の可能性も期待されます。

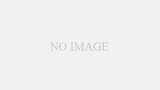
コメント